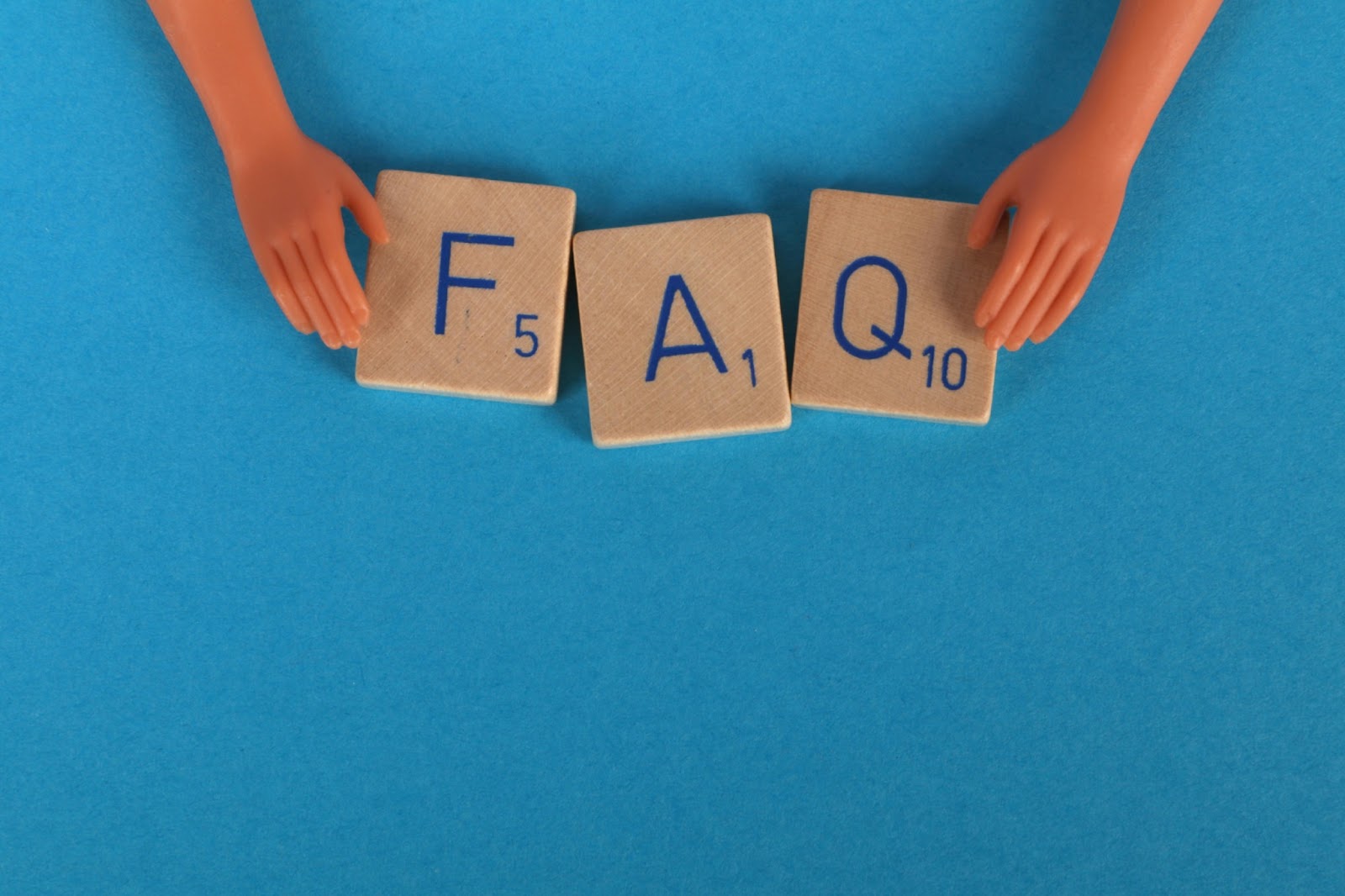
【重要】FAQとQ&Aはどう違う?自社に向いているのは?作り方の手順やポイントも!
業界トップの正確率で作業効率爆上げ!
FAQとQ&A。どちらもよく目にする言葉ですが、その「明確な違い」について皆さんはご存知ですか。実は、この2つは似て非なるもので、その目的や使われ方に「明確な違い」があるんです。
今回は「FAQとQ&A」に焦点を当て、その概要や意味・役割、主な種類と例、それぞれの違い・選び方などについて解説します。今後、FAQとQ&Aの作成を検討している方はぜひご一読ください。
FAQとは?
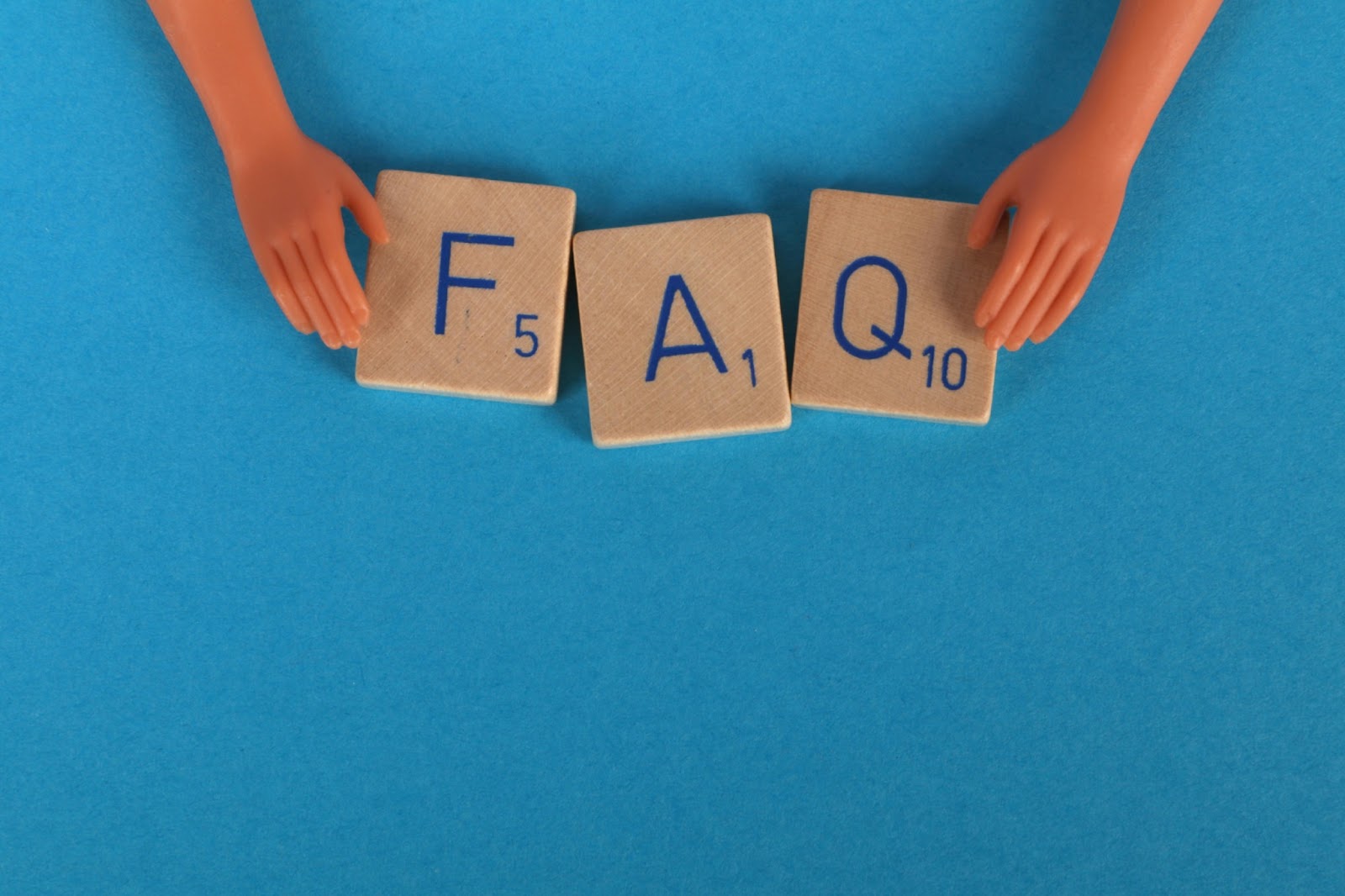
FAQとは、「Frequently Asked Questions」の略で、一般的には「よくある質問」とその回答をまとめたリストやページを指します。日本語では「エフエーキュー」と読みます。
FAQの意味・役割
FAQは、「よくある質問」だけを厳選して掲載する形式で、実際に頻繁に寄せられる問い合わせに重点を置きます。内容が狭く深いことが多く、対象となる顧客や従業員が最も疑問に感じやすい項目にフォーカスされています。FAQを設けることで、ユーザーは疑問を自己解決したり、企業側は問い合わせ対応の負担を減らしたりでき、その結果、顧客満足度の向上や業務の省力化につながります。
FAQの主な種類とその例
顧客向けFAQ:主に商品やサービスの利用時に出る疑問点を解消
Q.予約は当日でも可能ですか?
A.当日の空室状況によっては、フロントもしくはお電話にてご予約いただけます。Q.駐車場は利用できますか?
A.当ホテル専用の駐車場を〇台までご利用いただけます。Q.室内でインターネットは利用可能ですか?
A.全ての客室にLAN回線とWi-Fiを完備しております。
社内FAQ:主に業務上の手続きや社内ルールの確認など従業員の利便性向上を図る
Q.離席する際のルールを教えてください。
A.電話対応がない場合はトイレ休憩など自由に行えますが、「離席中」の札を立てるか、周囲の社員に離席の旨を伝えてください。昼休みや小休憩についてはマニュアルをご確認ください。Q.手当についての詳細を知りたいです。
A.就業規則の該当ページをご参照ください。Q.社内システムの〇〇の操作方法は?
A.操作手順を写真付きで解説していますので、社内ポータルを確認してください。
コールセンターFAQ:主に顧客対応の質向上やオペレーターの効率的な対応を支援
Q.商品の返品は可能ですか?
A.お届けした商品に破損や相違があった場合は、商品到着後7日以内にお客様センターまでご連絡ください。なお、お客様都合での返品はお受けいたしかねます。
Q.貸与されたスマートフォンが故障した場合はどうすればいいですか?
A.マニュアルを確認後、システム情報部にお問い合わせください。対応できない場合はマニュアルURLや問い合わせ先を参照してください。
Q.注文内容を確認したいです。
A.ご注文完了後にお送りしている「ご注文確認メール」からご確認いただけます。メールが見当たらない場合は、マイページの「注文履歴」からもご確認いただけます。
Q&Aとは?
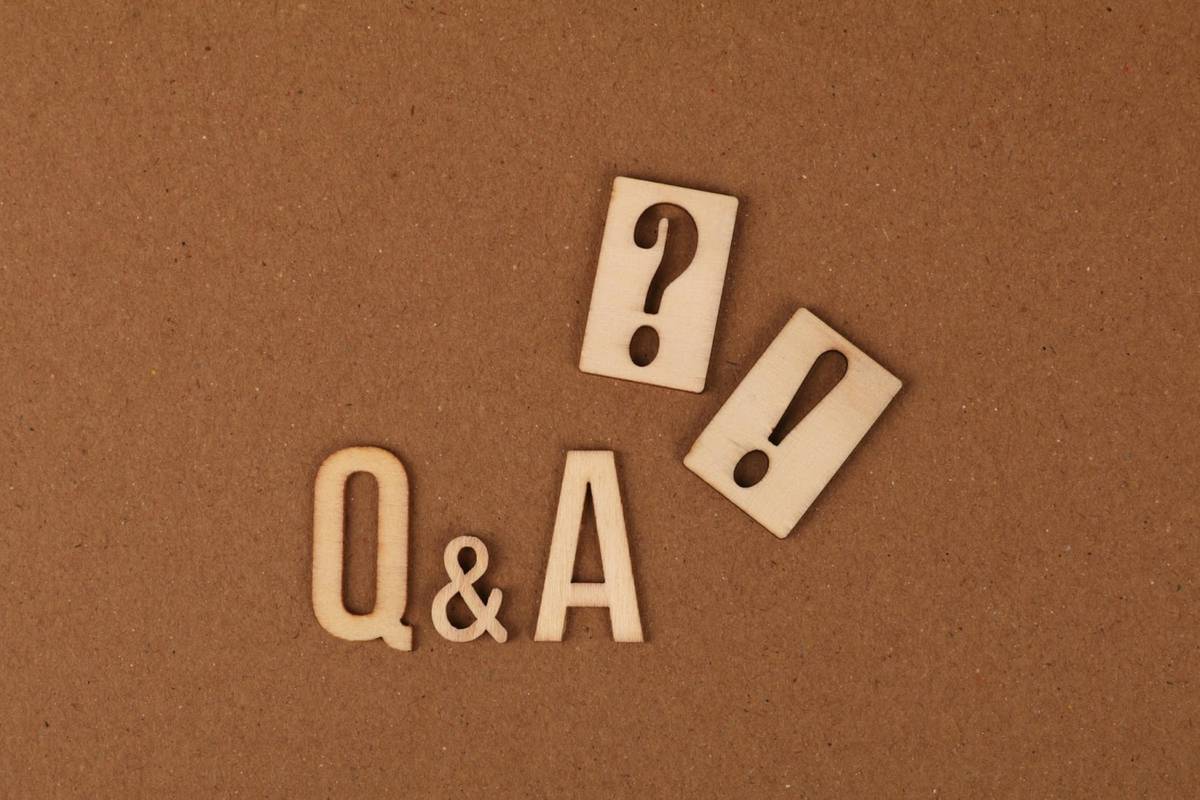
Q&Aとは、「Question and Answer」の略で、一般的には「質問と回答」という意味で使われます。日本語では、「キューアンドエー」と読みます。
Q&Aの意味・役割
Q&Aは、質問の頻度に関係なく、想定される質問や特殊なケースにも対応しており、問い合わせが予想される内容も含め網羅的に質問と回答が用意されています。主な目的は疑問や課題に対して直接的に答えを提示し、情報を分かりやすく整理することにあり、マニュアルや取扱説明書、Webサイトなどさまざまな場面で活用されます。
Q&Aの主な種類とその例
イベント・セミナー型Q&A:ライブイベントやセミナー、Webセミナーなどで出された質問にその場で回答する形式
Q.イベントの参加登録方法を教えてください。
A.公式Webサイトの参加申込フォームから必要事項を入力して送信してください。登録完了後、確認メールが届きます。Q.参加費はいくらですか?
A.基本的に無料ですが、一部のセミナーやワークショップは有料です。詳細はイベントページをご確認ください。Q.キャンセルしたい場合はどうすればいいですか?
A.登録完了メールに記載のキャンセルリンクから手続きをしてください。キャンセル期限はイベントの3日前までです。フォーラム型Q&A:インターネット上の掲示板やフォーラムで、ユーザーが質問を投稿し、他のユーザーや管理者が回答するパターン
Q.新しいソフトウェアのインストール方法について教えてください。
A.インストール手順は公式マニュアルの2ページ目に詳しく記載されています。わからない点があればさらに質問してください。Q.製品のバグを見つけました。どこに報告すればいいですか?
A.公式サポート窓口に連絡するか、フォーラムの「バグ報告」カテゴリに投稿してください。Q.この機能の使い方を教えてください。
A.〇〇さんが具体的な操作方法を詳しく説明してくれています。以下のリンクを参照してください。企業サポート型Q&A:カスタマーサポートが中心になり、利用者からの多様な問い合わせに一問一答で回答を提供
Q.サポートはどのように受けられますか?
A.24時間対応のサポートチケットシステムまたは電話で受付けています。お困りの際はサポートセンターまでご連絡ください。Q.サービスの料金プランについて教えてください。
A.詳細は料金表ページをご参照ください。ご不明点があればお問い合わせください。Q.データのセキュリティはどのように保護されていますか?
A.業界標準の暗号化技術を利用し、定期的な監査を実施しています。
FAQとQ&Aの違い
FAQとQ&Aは、どちらも「質問と回答」をまとめたものですが、厳密には以下のような違いがあります。特に、「質問頻度」と「掲載範囲」に明確な違いがあります。
| 特徴(観点) | FAQ | Q&A | 戦略的な意味合い |
|---|---|---|---|
| 目的と役割 | 問い合わせ件数の削減、顧客の自己解決促進 | 網羅的な情報提供、詳細な問題解決 | FAQはサポート業務の負荷軽減ツール。Q&Aはユーザーの知識向上ツール |
| 掲載範囲と深さ | 狭く深く:厳選された質問に高品質な回答 | 広く深く:多様な質問を網羅した辞書的存在 | 80対20の法則で最大効果を狙うか(FAQ)、あらゆる可能性を網羅する知識ベースを構築するか(Q&A) |
| 対象読者 | 顧客全般、社内担当者(新人など) | 特定の情報を求める専門的ユーザー、問い合わせ管理者 | FAQは大多数のユーザーに奉仕する。Q&Aは特定の高い意図を持つユーザーや社内の専門家に奉仕する |
| 活用シーン | カスタマーサポート、ECサイトの商品ページ | 製品マニュアル、技術的なナレッジベース | 製品の複雑性やユーザーからの問い合わせの性質によって選択が異なる |
FAQとQ&Aの選び方
FAQとQ&Aのどちらを選ぶべきかは、そのページの目的とターゲットによって決めるのが良いでしょう。
FAQ導入が向いている企業
顧客から同じような質問が頻繁に寄せられる企業
よくある質問をまとめることで問い合わせ負担を減らしたい企業
サービスの品質向上や効率的な顧客対応を目指す企業
など、FAQは問い合わせ内容が一定以上重複しやすい環境にある企業に向いています。
Q&A導入が向いている企業
幅広い質問に対応し詳細な情報を提供したい企業
複雑で多様な問い合わせが存在し、個別対応が必要な企業
製品やサービスのマニュアル的役割も果たしたい場合
など、Q&Aはより多様で個別性の強い質問対応を求められる企業に適しています。
【結論】どちらを作成すれば良いか迷った場合:まずはFAQから始める
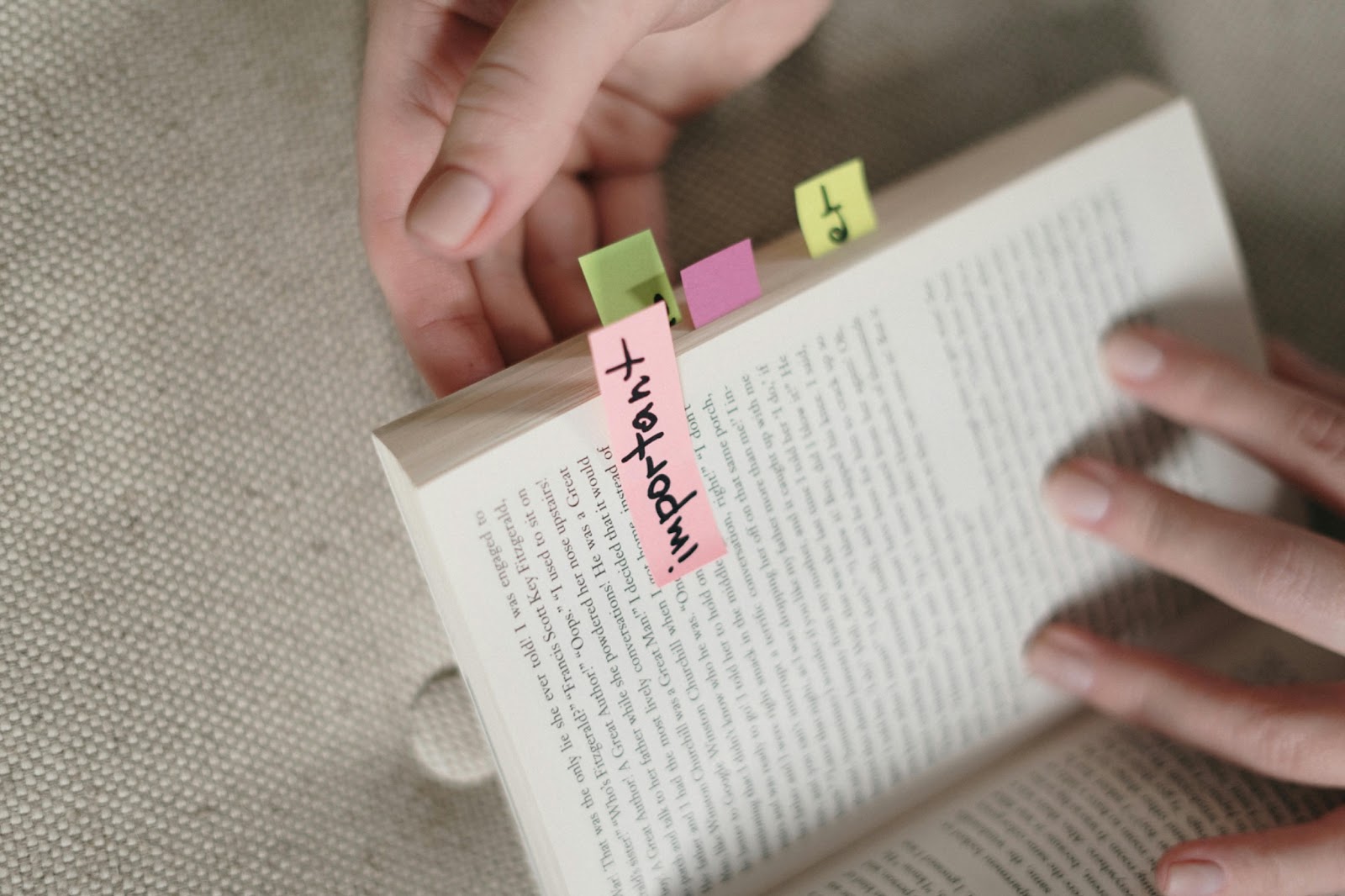
FAQは「よくある質問」とその回答を厳選して掲載しているため、作成コストも比較的抑えられ、効率的に問い合わせ対応の負担軽減が可能です。また、質問数が限られているため、個々の回答の質を高めやすく、利用者が求める情報に直結しやすいというメリットもあります。
Q&Aはより網羅的で広範囲の質問に対応できますが、その分作成やメンテナンスに手間がかかり、回答の専門性や質が落ちるリスクもあります。まずFAQを構築し、対応すべき頻出質問を整理・充実させた後、必要に応じてQ&Aに展開・拡張していく段階的な導入が一般的かつ効果的です。
FAQの導入効果
FAQの導入効果は多岐にわたり、主に5つのメリットがあります。
1.問い合わせ件数の削減と業務負担の軽減
FAQによって顧客が自力で問題を解決できるため、コールセンターやカスタマーサポートへの問い合わせ件数が減少し、オペレーターや担当者の業務負担が大幅に軽減されます。また社内向けFAQの場合も、内部問い合わせの削減により担当者が本来の業務やコア業務に集中できるようになります。
2.顧客満足度の向上
FAQを活用することで、スムーズかつ正確な顧客対応が可能となり、問い合わせへのレスポンスが早くなります。これにより顧客満足度が向上するだけでなく、トラブルの未然防止や企業イメージの向上、リピーター増加といった長期的な利益も期待できます。
3.業務ノウハウの蓄積と属人化防止
FAQに情報やノウハウを蓄積することで、特定の担当者だけに知識が偏る属人化を防ぎ、社内の知識共有を円滑にします。ベテランの退職による知識損失を防ぎ、新人教育効率化にも有効です。
4.コスト削減と業務効率化
問い合わせ対応の効率化により、必要な人員を削減でき教育コストも抑制されます。対応の均一化や早期自己解決が可能になることで全体の業務効率が向上するでしょう。
5.SEOやWeb集客への効果
FAQページの充実はWebサイトのアクセス増加につながり、サイト評価向上やSEO効果が見込めます。それにより、Web集客の強化も実現するでしょう。
FAQの作り方の手順
FAQの作り方の一般的な手順は以下の6ステップです。
1.質問と回答の材料を収集する
過去の問い合わせ内容(電話、メール、チャット、Webフォームなど)を洗い出し、よくある質問をリストアップします。加えて、製品説明書や社内マニュアル、スタッフからのヒアリングやアンケートなども活用します。
2.収集した質問項目の分析と整理
頻度や重要度に応じて質問を分類し、FAQに掲載すべき優先度の高い質問を決定します。この際、回答が不要なものや専門的すぎるものは除外します。
3.回答の作成と編集
わかりやすく簡潔に回答文を作成します。専門用語は可能な限り平易な表現に置き換え、必要に応じて関連ページや補足情報のリンクも用意します。統一感を保つための執筆ルール(レギュレーション)も策定すると良いでしょう。
4.レビューと承認
内容の正確性や誤字脱字のチェックを複数人で行い、精度を高めます。場合によっては専門部門の承認を得てから公開します。
5.公開と運用開始
FAQをWebサイトや社内ポータルに公開し、利用しやすい導線や検索機能の整備を行います。定期的にアクセス状況や問い合わせ件数を分析し、改善点を見つけて更新を続けます。
6.継続的な見直し・改善
新たな質問の追加や古くなった情報の修正などを定期的に実施し、最新かつ有用な情報維持に努めます。
FAQを作成する際のポイント

効果的で使いやすいFAQを作るために重要なポイントは以下の5つです。ぜひ参考にしてみてください。
1.より正確性のある最新情報にする
誤った情報や古い情報は、ユーザーの信頼を失う原因となります。製品やサービスの仕様、料金、手続きなどが変更された際は、すぐにFAQの内容を更新しましょう。問い合わせ履歴やサポート担当者からのフィードバックを定期的に確認し、ユーザーが本当に知りたい情報を正確に反映させることが重要です。
2.ユーザーファーストを意識する
FAQはユーザーの疑問を解消するために存在します。専門用語は避け、誰にでも理解できる平易な言葉で説明しましょう。また、見出しや箇条書き、画像、動画などを活用することで、文章を読むのが苦手な方でも内容を素早く理解できます。さらにスマートフォンからの閲覧が増えているため、モバイルでの見やすさも考慮すると、より多くのユーザーにとって使いやすいFAQになるでしょう。
3.キーワード検索に対応させる
ユーザーは疑問を解決するために、Googleなどの検索エンジンやFAQサイト内の検索機能を利用します。ユーザーが検索しそうなキーワードを予測し、質問タイトルや回答文に自然に盛り込むことで、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすくなります。
4.カテゴリーや分類を適切に設定する
FAQの項目が増えてきたら、カテゴリに分けて整理しましょう。たとえば「注文」「支払い」「配送」「返品」といったように、関連性の高い質問をカテゴリーごとにまとめることで、ユーザーはスムーズに情報を探すことができます。
5.表現を統一し運用しやすくする
チームでFAQを作成・管理する場合、用語や表現、ルールを統一しておくことが重要です。 「弊社」「当社」「私たち」といった呼称の統一や、質問形式(「〜ですか?」「〜する方法は?」など)を事前に決めておくことで、メンテナンスがしやすくなり、FAQ全体の品質も保ちやすいでしょう。
まとめ:FAQとQ&Aの違いを理解して効果的かつ効率的に使い分けよう!
今回は「FAQとQ&A」に焦点を当て、その概要や意味・役割、主な種類と例、それぞれの違い・選び方などについて解説しました。
FAQとQ&Aは一見似ているようで全く異なります。どちらをどのように活用すべきか、本記事を通してそのヒントを得ていただければ幸いです。自社のWebサイトの目的やユーザーのニーズに合わせて、これら2つを使い分け、より良いユーザー体験を提供していきましょう。
FAQとQ&A作成の「質問収集」を効率化しませんか? AI文字起こしサービス「Notta」のご紹介
効果的なFAQとQ&Aを作成するための第一歩は、顧客や社内から寄せられる「生の声」を正確に収集することです。しかし、電話での問い合わせ内容や、スタッフへのヒアリングを一つひとつ記録し、分析するのは大変な手間と時間がかかります。
そこでおすすめしたいのが、AI文字起こしサービス「Notta」です。
Nottaを使えば、顧客との通話や社内ミーティングの音声を、AIが自動で高精度にテキスト化します。
顧客サポートの通話を録音・テキスト化し、頻出する質問やキーワードを簡単に抽出。
社内ヒアリングの内容を文字起こしし、担当者への質問のネタを漏れなく収集。
テキスト化されたデータはキーワード検索が可能なため、質問の傾向分析もスピーディに行えます。
FAQとQ&A作成で最も重要な「材料収集」のプロセスをNottaで効率化し、より質の高い回答を作成する時間に充ててみてはいかがでしょうか。正確な情報収集が、ユーザー満足度の高いFAQ作りへと繋がります。
Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。
