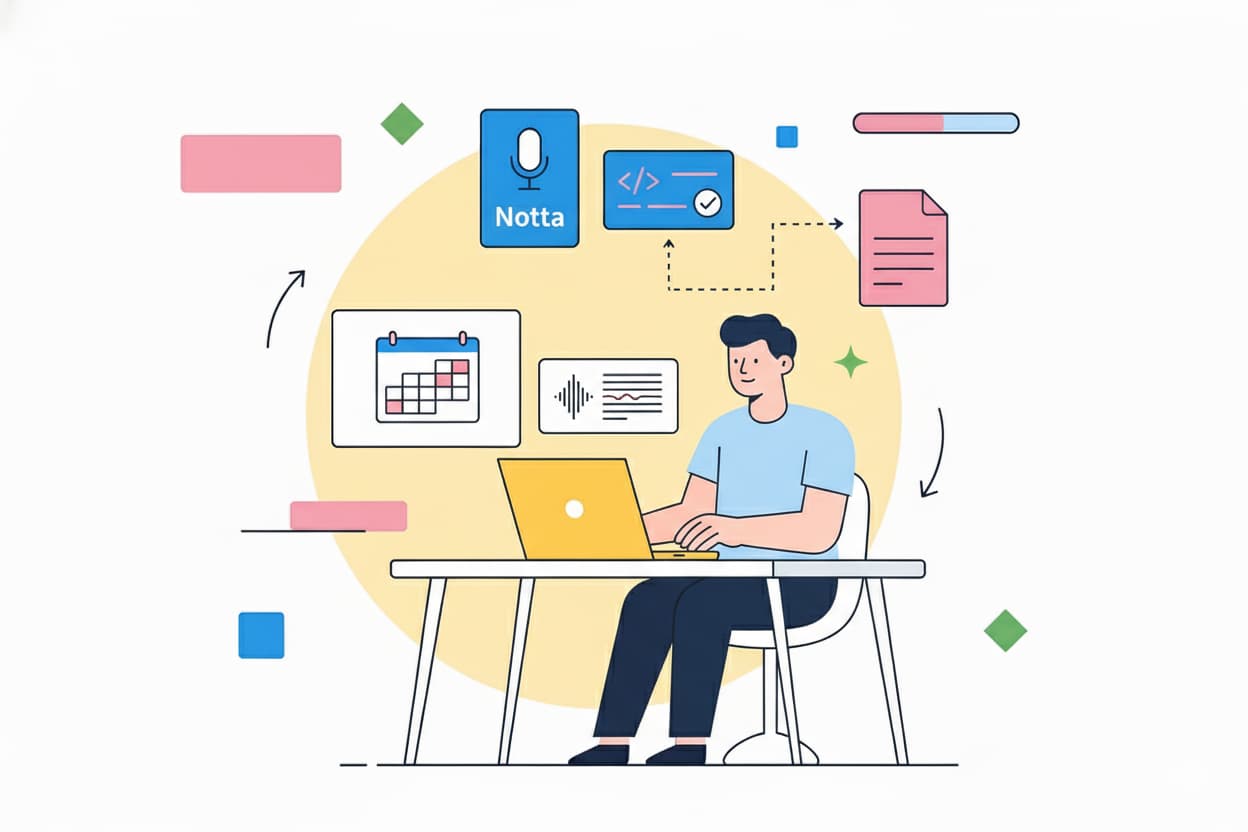
スマートオフィス推進で企業DXを加速|導入メリット・課題・成功事例
業界トップの正確率で作業効率爆上げ!
リモートワークやハイブリッドワークが定着した今、従来型のオフィスでは「生産性の低下」や「コミュニケーションの分断」といった課題が目立ち始めています。さらに、光熱費や賃料などの固定コストを最適化しつつ、社員のウェルビーイングを維持することも、企業にとって大きなテーマとなっています。
こうした中で注目されているのが、IoTやAIなどのテクノロジーで働く環境を最適化する「スマートオフィス」です。業務効率化だけでなく、データを活用した経営判断や社員体験の向上にもつながる仕組みとして、多くの企業が導入を進めています。
本記事では、スマートオフィスの仕組みやメリット、導入ステップ、成功事例までをわかりやすく解説します。
スマートオフィスとは?今なぜ注目されるのか

スマートオフィスとは、IoT・AI・クラウドなどのテクノロジーを活用し、働く環境をデータで最適化する次世代オフィスのことを指します。照明や空調を自動制御したり、会議室や座席の利用状況を可視化したりと、従業員の快適性と生産性の両立を実現します。
近年では、ハイブリッド勤務やフレキシブルワークの普及により、オフィスは単なる作業場所ではなく、人と情報がつながる経営インフラへと変化しています。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れの中で、オフィス空間のデジタル化は企業競争力の鍵を握るテーマとなっているのです。
DXと働き方改革が生んだ次世代オフィス
DXの目的は、業務のデジタル化にとどまらず、組織全体の生産性と価値創出の仕組みを変革することにあります。その中で、オフィスという「人と情報が交わる場所」をデータで管理・最適化することは、DX推進の重要な要素です。
同時に、働き方改革の浸透により「いつでも・どこでも働ける」環境づくりが求められるようになりました。スマートオフィスは、リモートワークや出社勤務を柔軟に組み合わせるハイブリッドワークを支える基盤としても注目されています。データに基づく空間設計や環境制御によって、社員一人ひとりが集中できる環境を維持しつつ、チーム全体の生産性を高めることが可能です。
スマートオフィス推進の背景と企業の課題
スマートオフィスが注目される背景には、人材不足やオフィスコストの上昇、ESG経営(環境・社会・ガバナンスを重視した持続可能な経営)への対応といった複合的な課題があります。
多くの企業で人材が不足するなか、限られたリソースで成果を最大化するには、働く環境の効率化が欠かせません。また、テレワークの普及により、会議室や座席の稼働率が低下するなど、「オフィスの使われ方」そのものを見直す動きも広がっています。さらに、エネルギー最適化や脱炭素への取り組みも、スマートオフィス導入を後押しする要因です。
つまり、スマートオフィスは単なるIT導入ではなく、経営課題を解決するための戦略的施策として位置づけられているのです。企業は今、テクノロジーを軸に「人がより良く働ける場」を再設計するフェーズに入っています。
スマートオフィス導入のメリットとは?

スマートオフィスは、単に設備をデジタル化するだけでなく、企業の生産性・働き方・組織文化を包括的に変革する仕組みです。ここでは、スマートオフィスの導入によって得られる具体的なメリットを6つの観点から解説します。
生産性向上と業務効率化
スマートオフィスの最大の魅力は、業務プロセスをデータで最適化できることです。たとえば、会議室の利用状況や座席の稼働率をセンサーで可視化することで、無駄なスペースを削減し、レイアウトを改善できます。
また、照明や空調を自動制御すれば、作業環境を常に快適に保ちながらエネルギーコストも削減可能です。
さらに、会議録の自動生成やAIによる議事要約など、情報共有の効率化も進みます。業務データの分析結果をもとに改善を繰り返すことで、「人に依存しない生産性向上」を実現できます。
働きやすい環境の実現
スマートオフィスは、ハイブリッドワークを支える基盤でもあります。
クラウド環境と会議室予約システムや勤怠管理ツール、デバイス管理などのオフィスシステムを連携することで、出社・在宅・サテライトオフィスなど、働く場所に縛られない柔軟な勤務体系を可能にします。会議室予約や出社管理を自動化すれば、社員同士のスケジュール調整もスムーズです。
このような仕組みにより、企業は多様な働き方を許容しつつ、チームの一体感を維持できます。結果として、採用・定着率の向上や離職防止にもつながるのが大きなメリットです。
社員ウェルビーイングの向上
近年注目されている「ウェルビーイング(心身の健康と幸福)」の観点でも、スマートオフィスは効果を発揮します。温度・照明・CO₂濃度などをセンサーで常時モニタリングし、社員が快適に過ごせる最適な環境を自動調整できるからです。
さらに、オフィス内の混雑状況を可視化することで、ストレスを感じにくいスペース利用を促進できます。働く環境が整うことで、社員の集中力や創造性が向上し、組織全体のパフォーマンスの最大化につながります。
コミュニケーションの促進
リモートワークが浸透した一方で、社員同士のつながりが薄れ、情報共有が滞るという課題を抱える企業も少なくありません。スマートオフィスはこの問題を、テクノロジーによる可視化と環境設計で解決します。
たとえば、会議室や共用スペースの利用状況をセンサーで把握し、チームが自然に交流できるレイアウトや動線をデータから導き出すことができます。さらに、オンライン会議を行える通信環境を整えることで、出社・在宅を問わずスムーズに意見交換できる環境を構築可能です。
このようにスマートオフィスは、物理的な距離を超えて人と情報をつなぎ、コミュニケーションを促進する仕組みとして機能します。
ストレスの軽減につながる
スマートオフィスは、働く環境を整えるだけでなく、日々の業務や通勤にともなうストレスを減らす仕組みとしても効果を発揮します。
まず、会議の予定や在席状況をシステムで一元管理することで、連絡の行き違いや場所調整の負担を軽減することが可能です。業務がスムーズに進めば、時間に追われる心理的なストレスを抑えられます。
また、クラウド環境の整備により、出社・在宅・サテライトオフィスなど働く場所を柔軟に選択できるため、通勤混雑や移動時間に伴うストレスの削減にもつながります。社員が安心して働ける柔軟な環境を整えることこそ、スマートオフィスの真価といえるでしょう。
企業価値の向上
スマートオフィスの導入は、単なる業務改善にとどまりません。データに基づく経営判断・省エネ・ESG対応・ブランディング効果など、企業価値の向上にも直結します。最新の環境を整えたオフィスは、顧客やパートナーに対しても「先進的で信頼できる企業」という印象を与えるでしょう。
また、社員の働きやすさを重視する企業姿勢は採用力を高め、持続可能な経営へとつながる重要な投資でもあります。スマートオフィスは、まさにDXと人的資本経営を両立させる新しい経営基盤といえるでしょう。
スマートオフィス導入前に知っておくべきデメリット・注意点

スマートオフィスは多くのメリットをもたらしますが、導入時にはいくつかの課題も存在します。効果を最大化するためには、こうしたリスクを理解し、あらかじめ対策を講じることが重要です。
高額な初期導入コストとROI評価の難しさ
スマートオフィスを実現するには、IoTセンサーの導入やシステムの構築、クラウド環境の整備などの初期費用がかかります。特に中小企業ではROI(投資対効果)の算出や費用対効果の見極めが難しい点が課題です。
そのため、導入目的を明確にし、「どの業務の効率化にどれだけ効果があるか」を数値化して検証しましょう。また、まずは会議室や勤怠管理からなど、段階的に導入すれば、初期負担を抑えつつ投資対効果を測りやすくなります。
セキュリティリスクの増大
IoT機器やクラウドサービスを多数活用するスマートオフィスでは、不正アクセスや情報漏えいのリスクが高まります。特に、社外からのアクセスを前提としたハイブリッド勤務環境では、社内外のすべてのアクセスを常に確認・検証する「ゼロトラスト」型のセキュリティ設計が欠かせません。
導入時には、以下を徹底することが重要です。
デバイスごとのアクセス権限設定
ID管理・多要素認証(MFA)の導入
ファームウェアやソフトウェアの定期更新
また、社員のセキュリティ教育を継続的に実施し、技術と人の両面でセキュリティを強化する体制を構築しましょう。
社員のITリテラシー不足と変化への抵抗
スマートオフィスの運用には、デジタルツールを扱うスキルや、新しい働き方への順応力が求められます。しかし、実際には「システム操作に不安を感じる」「使い方が複雑そう」といった社員の心理的抵抗が導入の障壁になることもあります。
この課題を解消するには、初期段階から社員を巻き込み、操作説明会やマニュアル整備を行うことが効果的です。「便利そうだから導入する」のではなく、現場が納得して使いこなせる状態をつくることが成功の鍵です。
既存設備との互換性とレガシーシステムの課題
社内にレガシーシステム(長年使い続けてきたシステムや通信設備)がある場合、新しいIoT機器や管理システムとの互換性が問題になることがあります。古いネットワーク環境では通信が安定せず、データが正しく連携できないケースも少なくありません。
そのため、導入前には現状のインフラを棚卸しし、どこを残し、どこを刷新するかの優先順位を明確にしましょう。一度にすべてを切り替えるのではなく、段階的な移行を行うことで、トラブルを最小限に抑えられます。
スマートオフィス導入のステップ

スマートオフィスは、単なる設備更新ではなく、業務設計や組織文化の変革を伴うプロジェクトです。ここでは、導入を成功させるための4つのステップを紹介します。
ステップ1:現状分析と課題の可視化
まず取り組むべきは、現在のオフィス環境や業務プロセスの“見える化”です。出社率や会議室稼働率、座席利用率、電力消費量などのデータを整理し、どの領域に無駄があるのかを明確にします。
この段階では、数値を完璧に揃える必要はありません。重要なのは、「感覚」ではなく「データ」に基づいて議論できる土台をつくることです。簡易的なアンケートやヒアリングも組み合わせることで、社員が抱えるストレスや不満を可視化できます。
ステップ2:目的設定と要件定義
次に、「なぜスマートオフィスを導入するのか」という目的を明確にします。多くの企業が陥りがちなのは、「便利そうだから導入した」という曖昧な動機です。
目的を定義する際は、自社がどの領域で成果を出したいのかを具体化しましょう。以下は、導入目的として多くの企業が重視する代表的な観点です。
生産性向上:業務効率や集中環境を最適化したい
コスト最適化:オフィススペースや光熱費を削減したい
体験価値向上:社員の働きやすさ・満足度を重視したい
目的が明確になれば、どの領域から着手すべきかが見えてきます。また、この段階で「やらないこと」を決めておくと、導入範囲がブレにくくなります。
ステップ3:PoC(実証実験)と社内合意形成
PoC(Proof of Concept/概念実証)は、小規模な環境で導入効果を検証する重要なプロセスです。いきなりスマートオフィスを全社へ導入するのではなく、まずは1フロアや特定部署など、限定的な環境でテスト運用を行いましょう。
この段階では、主に以下のような要素を数値で確認します。
実際に業務効率がどの程度改善されたか
システムの使いやすさに課題はないか
社員の満足度や利用率はどう変化したか
成功事例をデータで示すことで、経営層や管理部門を巻き込みやすくなります。現場の声を反映しながら改善を重ねることで、社内全体の理解と合意形成をスムーズに進められるでしょう。
ステップ4:ROI評価と全社展開判断
PoCの結果を踏まえ、投資対効果(ROI)を評価します。たとえば、照明や空調の自動制御によるエネルギーコスト削減率、会議室稼働率や出社率の最適化などを定量的に比較します。
ROIを算出することで、感覚的な判断ではなく、経営判断として導入可否を検討できるようになります。この結果をもとに、ベンダー選定やシステム拡張、人材育成を含む中期ロードマップを策定し、全社展開を進めましょう。
IoT・センサー活用で実現するスマートオフィス

スマートオフィスの中核となるのが、IoTを活用したデータ収集と最適化の仕組みです。人の動きや環境データをリアルタイムで把握することで、これまで感覚に頼っていたオフィス運営を科学的にマネジメントできるようになります。
ここでは、IoT・センサーを活用した代表的な施策を紹介します。
会議室利用状況の把握とヒートマップ化
オフィスの中でも利用頻度が偏りやすいのが会議室です。IoTセンサーを設置することで、会議室の稼働率や利用人数をリアルタイムで把握でき、予約システムと連携すれば空き状況をリアルタイムで共有可能になります。
さらに、利用データをヒートマップとして可視化することで、「頻繁に使われる会議室」「空きがちなエリア」といった傾向を定量的に分析できます。これにより、会議室の数や配置を最適化し、スペース活用効率と業務生産性の向上につなげることが可能です。
室内環境・座席温度のリアルタイム管理
温度・湿度・照度・CO₂濃度などの環境データをセンサーで自動収集し、AIが最適な状態を維持します。これにより、快適な作業環境を人手を介さずに保つことが可能になります。
特に座席やエリアごとに温度をリアルタイムで監視すれば、冷暖房の過剰運転を防ぎ、エネルギーコストを抑制することも可能です。また、社員の集中力を妨げる「暑すぎる・寒すぎる」といった不快感を軽減し、生産性と省エネを両立するオフィス運用を実現します。
不審者や異常検知による安全性向上
IoTカメラや人感センサーを連携させることで、入退室の異常検知や不審者の侵入を自動で検知できます。たとえば、深夜や休日に想定外の動きがあった場合、即座に管理者へアラートを通知し、迅速に対応することも可能です。
また、火災や停電などの異常を検知した際にも、センサー情報をもとに関係部署へ自動通知できる仕組みを構築することで、人的被害や設備トラブルのリスクを最小化します。安全性を確保することは、社員の心理的安心感を高めるうえでも欠かせません。
導入後のデータ分析と改善サイクル
IoTセンサーによって収集されたデータを分析し、オフィス運用の改善点を継続的に洗い出すことで、PDCAサイクルを回しながら最適化を進められます。たとえば、稼働率の低いエリアを共有スペースに変更したり、温度変動が大きい箇所に追加センサーを設置したりと、データを根拠とした改善が可能です。
この「測定→分析→改善」のサイクルを継続することで、オフィス環境を常に最適な状態に保ち、運用の成熟度を高めていくことができます。
スマートオフィス推進の第一歩:Nottaで会議の「時間」と「情報」をスマート化する

スマートオフィス化を進める上で欠かせないのが、日々の業務データをどれだけ効率的に活用できるかという視点です。その第一歩として注目されているのが、AI文字起こしツール「Notta」です。
Nottaを活用して会議や打ち合わせの音声を自動でテキスト化し、チーム全体で共有・分析できる環境を整えることで、情報の見える化と時間の最適化を同時に実現します。
Nottaとは?会議の自動文字起こしで生産性を劇的に向上させるAIツール
Nottaは、音声をリアルタイムで文字に変換するAI文字起こしプラットフォームです。Zoom・Google Meet・Microsoft Teamsなど主要なオンライン会議ツールと連携し、発言内容を自動でテキスト化します。
また、日本語・英語をはじめ多言語に対応しており、発話者ごとの識別やタイムスタンプ付与にも対応しています。これにより、正確で検索性の高い議事録データを手間なく生成することが可能です。
Nottaを使えば、従来のように録音を聞き直したり、議事録を手作業でまとめたりする必要はありません。会議中にリアルタイムで内容を可視化し、必要な情報だけをすぐに共有できます。
議事録作成の時間をゼロに:スマートオフィスにおけるNottaの具体的な価値
スマートオフィスの目的は、社員が創造的な業務に集中できる環境を整えることです。Nottaはその中で、時間のかかる「議事録作成」を完全に自動化します。
会議終了と同時に文字起こしデータが完成し、共有リンクを発行すればチーム全員が即時にアクセス可能です。検索機能により、過去の会議内容からキーワード・発言者を瞬時に抽出することもできます。
これにより、会議後の時間を「記録のため」ではなく「意思決定のため」の時間にシフトでき、プロジェクト進行・顧客対応・ナレッジ共有など、業務全体のスピードと透明性を高めます。
データ活用基盤の強化:会議情報をビジネス資産に変えるNottaの機能
スマートオフィスの本質は、「情報を資産として活かす」ことにあります。Nottaでは、文字起こしデータをもとにAI要約・タグ付け・テーマ抽出を自動で行い、会議内容を整理されたナレッジとして蓄積することができます。
さらに、社内クラウドやタスク管理ツール(Notion、Slack、Google Driveなど)との連携により、議事録をプロジェクトごとに整理し、社内データベースとして活用できる仕組みを構築可能です。
こうしたデータ活用基盤を整えることで、会議記録が単なるログではなく、意思決定・教育・改善のサイクルを支える「ビジネス資産」へと変わります。Nottaはまさに、スマートオフィス推進における最初のデジタル変革ポイントといえるでしょう。
スマートオフィス成功事例と学び

スマートオフィス化を検討する企業にとって、実際に成果を出している事例を知ることは非常に重要です。ここでは2つの成功事例と、そこから学べる成功のコツを紹介します。
AI清掃ロボット導入事例
ある大手オフィスビルにおいて、清掃スタッフの作業負担と清掃品質の維持が課題となっていました。そこで、そのビルでは自律走行型の清掃ロボットを導入し、床面清掃作業の自動化を進めました。
ロボットは障害物を検知しながら最適なルートを走行し、深夜や人の少ない時間帯にも清掃を行える仕様です。導入後、清掃スタッフは従来の床磨き・拭き掃除といった定型作業から解放され、什器の拭き上げや共有スペースの衛生管理など、付加価値の高い作業に集中できるようになりました。
さらに、この取り組みはオフィスで働く社員にも好影響を与えています。たとえば、清掃中の騒音や作業中の混雑が減少し、会議や集中作業への邪魔が少なくなりました。結果的に、集中できる環境や快適に働ける空間の実現につながっています。
新規オフィスIoTセンサー導入事例
あるスマートシティ内の実証オフィスでは、温度・湿度・CO₂濃度、座席や会議室の利用状況などをリアルタイムで可視化するIoTセンサー群を導入しました。各種データはクラウド上で一元管理され、換気や空調の制御、混雑の可視化、利用率の分析などに活用されています。
これにより、感染症対策と快適性の両立を実現し、社員が安心して働ける環境を整備しました。さらに、データを活用した運用改善によって、省エネやスペース最適化などの効果も確認されています。
成功企業に共通する導入のコツ
スマートオフィス導入を成功させている企業に共通するのは「目的を明確にしたテクノロジー活用」です。AIやIoTを導入すること自体が目的ではなく、業務課題や働きやすさの改善といった“解決したいこと”を起点に設計されています。
また、導入後もデータを活用して運用を継続的に見直している点も特徴です。利用状況や社員の反応を分析し、改善を重ねることで、システムを単なる仕組みではなく「成長するオフィス環境」へと進化させています。
さらに、経営層と現場が一体となって推進する体制づくりも欠かせません。経営が方向性を示し、現場が主体的に活用を進めることで、真の働き方改革が実現します。
日本のスマートオフィス普及率と今後のトレンド

働き方の変化やオフィス環境の進化に伴い、スマートオフィスへの関心は高まっています。国内外の市場動向を整理しながら、今後日本企業が取るべき導入戦略もあわせて見ていきましょう。
国内外比較と普及ステージ
海外では、スマートオフィスはすでに「成長期から普及期」に移行しています。とくに北米や欧州では、IoTセンサーやエネルギー管理システム、顔認証による入退室管理などの導入が急速に進み、2024年時点でグローバル市場規模は約5,390億円(約53.9 billion USD)、2030年までに年平均13.9%の成長が見込まれています。なかでも北米は全体の約3分の1以上を占め、すでにオフィスDXの中心地域といえるでしょう。
参考:スマートオフィス市場規模、シェア、成長レポート(2030年)
一方、日本では、明確なスマートオフィス導入率に関する統計はまだ整っていません。しかし、サテライトオフィスやIoTセンサー導入など部分的なスマート化は確実に進展しており、特に大企業を中心に働き方改革やESG経営の一環として投資が拡大しています。
中堅・中小企業ではROI(投資対効果)の評価やIT人材不足が課題となる一方で、クラウド基盤やAIツールの低コスト化により、2025〜2030年にかけて本格的な普及期を迎えると考えられます。
成長を支える市場要因
日本市場の成長を後押ししているのは、以下の3つの要因です。
ハイブリッド勤務の定着:出社と在宅を組み合わせた柔軟な働き方に対応するため、オフィス利用状況の可視化ニーズが拡大している。
エネルギー効率・ESG対応への関心:電力・CO₂削減の観点から、照明・空調・設備の自動制御技術が注目されている。
AI・IoT技術の低コスト化:クラウド連携やセンサー技術の普及で、中堅企業でも導入が容易になっている。
特に、政府が掲げる「Society 5.0」や地方自治体のスマートシティ政策が、スマートビル・スマートオフィスの推進を後押ししています。これらの取り組みにより、オフィスのデジタル化が「先進企業の取り組み」から「一般企業の経営課題」へと移行しつつあります。
今後の導入タイミングと戦略
国内市場では、今後5年が導入拡大の分岐点となると考えられます。今動く企業が、データ活用と業務改善の両面で先行者優位を得るでしょう。
特に以下の3つの戦略が重要です。
段階的な導入:会議室予約や環境管理などスモールスタートで効果を検証し、全社展開へ拡張する。
データドリブン経営との連携:IoTで得たデータを業務改善やコスト最適化に活かすす。
経営層のリーダーシップ強化:設備更新ではなく「DX推進プロジェクト」として位置づけ、組織横断で推進する。
スマートオフィスは、単なるオフィス改革ではなく「働き方そのものをアップデートするDXの基盤」です。導入のタイミングを逃さず、今から準備を進めることが競争力の維持につながります。
よくある質問(FAQ)

ここでは、スマートオフィスに関してよく寄せられる質問をもとに、導入前に押さえておきたいポイントをQ&A形式で整理しました。
スマートオフィス推進を成功させるための社内体制づくりとは?
スマートオフィスの導入を成功させるには、IT部門だけで完結させないことがポイントです。人事・総務・経営企画・情報システム部門など、複数部署が連携し、目的や評価指標を共有する体制を構築しましょう。
特に初期段階では、プロジェクト責任者を明確にし、社内を横断したワーキンググループを設けるとスムーズです。また、導入後も定期的に利用者アンケートやデータ分析を行い、現場の声を反映させるサイクルを回すことが、長期的な定着につながります。
スマートオフィス導入に利用できる補助金や支援制度はある?
国や自治体では、DXや働き方改革を後押しするための各種補助金が利用できます。代表的なものには、IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金などがあり、IoTデバイスやクラウドツールの導入費用が対象となるケースがあります。
また、都道府県・市区町村レベルでも「スマートオフィス化支援」「テレワーク環境整備補助」などの地域独自の制度が設けられている場合があるため、導入前に最新情報を確認しておきましょう。
スマートオフィスを中小企業で導入する際の注意点は?
中小企業の場合、課題になりやすいのは費用対効果と運用体制です。限られた予算や人員の中で一度に多くの仕組みを導入すると、管理負担が増し、かえって効果を測りにくくなることがあります。
そのため、まずは影響が大きく、成果を測定しやすい領域から段階的に導入することが重要です。たとえば、会議室予約や入退室管理など、業務効率に直結する領域から着手し、実績をもとに範囲を広げていくと無理なく定着させられます。
スマートオフィスの効果をどう測定・可視化できる?
スマートオフィスの効果を測定するには、定量データと定性データの両面から評価することが重要です。
定量的には、会議室利用率や出社率、エネルギー使用量、フリーアドレス席の稼働率などをIoTデータなどから可視化できます。定性的には、従業員アンケートやエンゲージメントスコアなどで満足度を測るのが一般的です。
こうしたデータを定期的にダッシュボードにまとめ、改善施策に活かすことで、投資効果を高められます。
スマートオフィス推進におけるNottaの活用メリットとは?
スマートオフィス推進の第一歩として、会議の効率化や情報共有の最適化から着手する企業が増えています。
Nottaは、会議音声を自動で文字起こしし、リアルタイムで共有できるAIツールです。議事録作成や情報整理の手間を削減し、会議後すぐに意思決定やアクションへつなげられます。
また、蓄積された会議データを検索・分析することで、組織全体のナレッジ共有や業務の透明化を促進できる点も、スマートオフィスの基盤づくりにおいて大きな価値があります。
まとめ|スマートオフィス推進で企業DXを加速
スマートオフィスは、単なるオフィスのデジタル化ではなく、働く環境そのものを再設計する取り組みです。IoTやAIを活用して業務効率や快適性を高めることはもちろん、社員のウェルビーイング向上やESG経営への貢献にもつながります。
導入にあたっては、明確な目的設定と段階的な実施、そして効果の可視化が成功の鍵となります。まずは会議や情報共有といった身近な業務からデジタル化を進めることで、スムーズに変革を始められるでしょう。
AI文字起こしツールの Notta を活用すれば、会議内容を自動で記録・共有でき、議事録作成や情報整理の手間を大幅に削減できます。スマートオフィスの第一歩として、時間と情報の無駄をなくす仕組みづくりから始めてみてはいかがでしょうか。
Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。