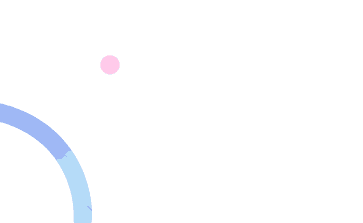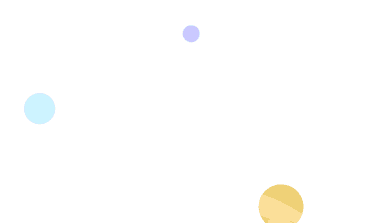営業職がきつい・やめとけといわれる理由!楽しすぎなのは向いている人だけ?

顧客エンゲージメントとは?具体的な高め方やメリットを徹底解説
業界トップの正確率で作業効率爆上げ!
最近よく耳にする「顧客エンゲージメント」という言葉。その正確な意味や、なぜビジネスで重要視されるのか、疑問に思っていませんか。商品やサービスが溢れる現代において、顧客との関係性を深めることは、企業の成長に欠かせない要素となっています。
この記事では、顧客エンゲージメントの基本的な定義から、似た言葉である顧客ロイヤリティやCXとの違いまで、分かりやすく解説します。
さらにエンゲージメントを高めることで得られる具体的なメリットや、明日から実践できる7つのステップ、効果を測るための指標もあわせて紹介します。最後まで読めば、自社に合った改善の第一歩を踏み出せるようになるでしょう。
顧客エンゲージメントとは

顧客エンゲージメントとは、企業と顧客との間に生まれる、深い信頼関係や愛着を指します。顧客エンゲージメントは企業と顧客が共に成長していくための大切な土台となります。
ロイヤリティとの違い
顧客エンゲージメントとロイヤリティの大きな違いは、関係性の向きにあります。結論として、ロイヤリティが顧客から企業への一方的な忠誠心であるのに対し、エンゲージメントは双方向の積極的な関わり合いを指します。ロイヤリティが高い顧客は、特定の商品を繰り返し購入してくれるかもしれません。しかし、必ずしも企業との対話を望んでいるわけではないのです。
一方でエンゲージメントは、顧客が企業の活動に興味を持ち、意見を伝えたりする行動を含みます。例えば、お気に入りのカフェに通い続けるのがロイヤリティです。対して、そのカフェの新メニュー開発アンケートに協力したり、SNSで応援したりするのはエンゲージメントと言えます。したがって、エンゲージメントはロイヤリティの概念を含みながらも、より深く、相互に影響し合う関係を示す言葉です。
CXとの違い
顧客エンゲージメントとCX(顧客体験)は、結果と手段の関係にあります。CXが良い体験を提供するための「手段」であり、その積み重ねによって生まれる「結果」が顧客エンゲージメントです。CXは、顧客が商品を認知し、購入を経て、利用後のサポートを受けるまでの一連の体験すべてを指します。質の高いCXを提供し続けることで、顧客は企業に対して満足感や信頼感を抱くようになります。
この感情の積み重ねが、最終的に企業への強い愛着、つまり顧客エンゲージメントという深い結びつきに発展するのです。例えば、ウェブサイトが使いやすかったり、店員の対応が親切だったりすることは、良いCXの一部です。素晴らしい体験を通じて、顧客は「この会社を信頼できる」と感じ、結果として「また利用したい」というエンゲージメントが育まれます。
CSとの違い
顧客エンゲージメントとCS(顧客満足度)は、評価する時間軸と関係の深さが異なります。CSは商品購入時など、特定の時点での満足度を測る短期的な指標です。対して、エンゲージメントは満足を超えた、長期的な信頼関係を示します。CSは、顧客の期待をどの程度満たせたかを表すものです。しかし、一時的に満足度が高くても、それが次の購入やブランドへの愛着に直結するとは限りません。
一方、エンゲージメントは、満足を土台とした上で、共感や信頼といった感情的なつながりを評価する、より長期的な視点を持っています。例えば、価格の安さで得られる満足はCSです。しかし、エンゲージメントが高ければ、多少価格が変動してもそのブランドを選び続けてくれるでしょう。つまり、CSはエンゲージメントを高める要素の一つですが、エンゲージメントはより持続的な関係性を指す概念なのです。
顧客エンゲージメントが重要な理由

LTV最大化
顧客エンゲージメントを高めることは、LTV(顧客生涯価値)を最大化させることに直接つながります。LTVとは、一人の顧客が取引を始めてから終わるまでの間に、企業にもたらしてくれる利益の総額を示す指標です。企業やブランドに強い愛着を持つ顧客は、商品を繰り返し購入してくれます。さらに、関連商品やより高価格帯のサービスにも興味を示しやすくなるでしょう。
例えば、あるスマートフォンのファンは、新型モデルが出るたびに買い替えるだけでなく、同じブランドの周辺機器も購入するかもしれません。エンゲージメントが高いほど、顧客は長きにわたり、より多くの利益をもたらしてくれる存在になります。
非価格差別化
顧客エンゲージメントは、価格以外の価値で他社との差をつける「非価格差別化」を実現する上で、非常に重要な役割を果たします。商品の機能や品質は、すぐに他社に真似されてしまい、結果として値下げ競争に陥ることが少なくありません。しかし、顧客との間に築かれた信頼関係やブランドへの愛着といった感情的なつながりは、他社が簡単に真似できるものではないです。
例えば、あるカフェの店員との会話を楽しみに通う顧客がいるとします。その顧客にとって、コーヒーの価格以上に、その店で過ごす時間そのものに価値を感じているのです。このような付加価値は、他店が安売りをしても揺らがない、強固な差別化の要因となるでしょう。
マーケティングコストの削減
顧客エンゲージメントを高めると、マーケティングにかかる費用を効率化し、削減することにつながります。一般的に、新しい顧客を一人獲得するためにかかる費用は、既存の顧客との関係を保つ費用の約5倍と言われています。エンゲージメントの高い顧客は、自社の商品やサービスを継続して利用してくれる優良な存在です。
そのため、常に多くの費用をかけて新規顧客を探し続ける必要がなくなります。結果として、事業への投資効率を高めることが可能になるのです。さらに、エンゲージメントの高い顧客は、SNSや口コミで自発的に商品を勧めてくれることがあります。これは、企業が費用をかけずに行える、非常に信頼性の高い宣伝活動と言えるでしょう。
顧客エンゲージメントを高めるメリット

購入頻度/継続率の向上
顧客エンゲージメントが高まると、顧客の商品購入頻度やサービスの継続率が向上します。企業やブランドに対して強い愛着や信頼を感じている顧客は、他の選択肢に目が向きにくくなるからです。何かが必要になった際、自然と「いつも利用しているあの会社の商品を選ぼう」と考えるようになります。このような指名での購入は、企業にとって安定した売上の基盤を築く上で非常に重要です。
例えば、ある化粧品ブランドのファンは、基礎化粧品からメイク用品まで同じブランドで揃えようとするかもしれません。また、サブスクリプションサービスでは、サービス内容への満足感に加え、運営会社への信頼から解約せずに利用を続けてくれるでしょう。顧客との結びつきを強くすることは、一度きりの顧客を生涯のファンへと育てる効果があります。
口コミ・UGC拡散による新規獲得
顧客エンゲージメントの向上は、口コミやUGCの拡散を通じた、新規顧客の獲得に大きく貢献します。UGCとは、顧客がSNSへの投稿やレビューサイトへの書き込みなど、自発的に作成するコンテンツのことです。商品やサービスに強い愛着を持つ顧客は、「この製品の良さを他の人にも伝えたい」という気持ちから、積極的に情報を発信してくれます。
そのため、UGCはまだ商品を知らない人の購買意欲を強く刺激するのです。例えば、あるレストランに感動した顧客が料理の写真をSNSに投稿すると、それを見た友人が「今度行ってみよう」と思うかもしれません。これは、企業が広告費をかけずに新しい顧客を得られるということです。
サポートコストの削減
顧客エンゲージメントを高めることは、顧客サポートにかかる費用や手間を削減する効果ももたらします。企業との関係性が深い顧客は、製品やサービスへの理解度も高い傾向にあるからです。そのため、簡単な疑問が生じた場合でも、企業のウェブサイトにあるFAQなどを自分で調べて解決してくれることが多くなります。結果として、コールセンターや問い合わせ窓口への連絡件数が減少し、対応に必要な人員や時間を節約できるのです。
さらに、顧客同士のオンラインコミュニティなどが活発になれば、より効果は高まります。ベテランの利用者が初心者の質問に答えるなど、顧客同士で問題が解決される場面も増えるでしょう。このように、顧客との良好な関係は、企業の運営効率を改善する上でもメリットがあります。
顧客エンゲージメントを測る指標

NPS®
NPS®(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客エンゲージメントを測るための代表的な指標です。これは「この企業(商品やサービス)を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」というシンプルな質問によって、顧客の推奨度を数値化します。単なる満足度ではなく、「他者に薦めるか」という未来の行動意向を問うことで、顧客の深い愛着や信頼の度合いを測ることができます。
質問に対して0から10の11段階で回答してもらい、9〜10点を「推奨者」、7〜8点を「中立者」、0〜6点を「批判者」と分類します。そして「推奨者」の割合から「批判者」の割合を差し引いた数値が、NPS®のスコアです。このスコアが高いほど、顧客エンゲージメントが高い状態と判断できます。
LTV
LTV(Life Time Value/顧客生涯価値)も、顧客エンゲージメントを測る上で非常に重要な指標です。LTVは、一人の顧客が企業との取引を開始してから終了するまでの全期間で、自社にどれだけの利益をもたらすかを示します。顧客エンゲージメントが高いほど、顧客は商品を繰り返し購入したり、長期間サービスを継続利用したりする傾向が強くなります。そのため、LTVの数値はエンゲージメントの高さに比例して大きくなるのです。
LTVを定期的に計算することで、エンゲージメント向上のための取り組みが、きちんと収益に結びついているかを確認できます。例えば「平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間」といった式で計算し、施策後に数値が伸びていれば、その施策は成功していると判断できるでしょう。
リピート率
リピート率とは、一度商品を購入した顧客が、再びその企業から商品やサービスを購入する割合を示す指標です。この数値は、顧客エンゲージメントの高さを判断する上で、分かりやすく直接的な手がかりとなります。顧客が商品を再購入するという行動は、最初の購入で得た体験に満足し、その企業やブランドに良い印象を持っている証拠です。
リピート率が高いということは、顧客が定着し、ファンになりつつあることを示唆しています。逆にエンゲージメントが低ければ、顧客は一度きりの利用で離れてしまうでしょう。例えば、ある期間に購入した全顧客のうち、2回以上購入した顧客の割合を計算することでリピート率を求めます。この数値を定期的に観測することで、施策の効果を測ることが可能です。
解約率
解約率(チャーンレート)とは、一定の期間内にサービスや契約を解約した顧客の割合を示す指標です。特に、月額制のサブスクリプション型ビジネスにおいて、顧客エンゲージメントの状態を測る重要な指標として用いられます。顧客がサービスを解約する背景には、サービス内容への不満や、企業との関係性が薄れてしまったことなどが考えられます。
そのため、解約率が高い状態は、顧客エンゲージメントが低下している危険信号と捉えるべきです。逆に、解約率が低い水準で安定していれば、多くの顧客がサービスに満足し、継続して利用したいと感じている証拠になります。この数値を毎月追跡し、解約の背景にある原因を探ることが、サービス改善のヒントにつながるのです。
顧客エンゲージメントを高める7ステップ

タッチポイント全体のCX設計
エンゲージメント向上の最初のステップは、タッチポイント全体でのCX(顧客体験)を設計することです。タッチポイントとは、広告やウェブサイト、店舗、SNS、購入後のサポートなど、顧客が企業と接するあらゆる機会を指します。これらの体験に一貫性がなく、どこか一つでも顧客に不満を感じさせてしまうと、企業全体の印象が悪化しかねません。
すべての接点で一貫して良い体験を提供することが、顧客との信頼関係を築くための土台となります。まずは、顧客が商品を認知してから利用するまでの一連の流れを可視化します。そして、各接点で顧客が何を考え、何を感じるかを想像し、最高の体験を計画的に提供することから始めましょう。
パーソナライズとデータ活用
次に重要なステップは、顧客データを活用し、一人ひとりに合わせたパーソナライズされた体験を提供することです。すべての顧客に同じ画一的な情報やサービスを提供しても、なかなか心には響きません。「自分のことをよく理解してくれている」と顧客に感じてもらうことで、企業に対して特別な親近感を抱いてもらえます。
具体的な例としてはECサイトで過去に購入した商品に関連する新製品をおすすめしたり、誕生月に特別なメッセージを送ったりすることが挙げられます。このような細やかな配慮の積み重ねが、顧客の心を掴むのです。
双方向コミュニケーション
企業からの一方的な情報発信で終わらせず、顧客と対話する双方向のコミュニケーションを心がけることが大切です。顧客は、自分の意見や感想を聞いてもらい、企業活動に参加しているという実感を得ることで、より強い結びつきを感じます。企業が顧客の声に真摯に耳を傾け、誠実に応える姿勢を見せることで、両者の信頼関係は着実に深まっていくのです。
実際の例で言うと、SNSで顧客からのコメントに丁寧に返信したり、新商品開発に関するアンケートを実施したりするのがおすすめです。顧客を単なる買い手としてではなく、共にブランドを創るパートナーとして扱う姿勢が、エンゲージメントを高める上で欠かせません。
VoC収集とプロダクト改善
顧客の声(VoC:Voice of Customer)を積極的に集め、それを製品やサービスの改善に活かす仕組みを作りましょう。顧客は、自分の出した意見や要望が実際に反映されることで、企業が自分たちを大切にしてくれていると感じます。また、顧客の声を基に改善を行うことで、製品はより顧客のニーズに合ったものになり、満足度も向上します。この良い循環が、エンゲージメントを強固なものにするのです。
アンケートやレビュー、問い合わせ窓口に寄せられる意見などを体系的に収集し分析しましょう。そして、「この機能が使いにくい」といった声が多ければ、次のアップデートで改善し、その事実を顧客に報告します。「私たちの声が届いた」と実感してもらうことが、信頼関係をさらに深めることにつながります。
エモーショナルなストーリーテリング
商品の機能やスペックといった事実情報だけでなく、顧客の感情に訴えかけるストーリーテリングを取り入れることも有効です。人は論理だけで動くのではなく、感情によっても心を動かされます。企業の創業秘話や開発者の情熱、製品が顧客の生活をどのように豊かにするかといった物語は、顧客の強い共感を呼び起こします。このような感情的なつながりは、スペックの比較だけでは得られない、ブランドへの特別な愛着を生み出す力があるのです。
自社のウェブサイトやブログで、製品開発の裏側にある苦労や想いを伝える記事を公開してみるのもおすすめです。また実際に製品を利用している顧客の感動的なエピソードを紹介することも、他の顧客の心を動かすでしょう。「この会社を応援したい」という気持ちを育むことが狙いです。
リアル×デジタルの統合体験
オンライン(デジタル)とオフライン(リアル)の体験をスムーズに連携させ、顧客に一貫したサービスを提供することが求められます。現代の顧客は、オンラインとオフラインを自由に行き来しながら情報を集め、商品を購入します。これらの体験が分断されていると、顧客は不便さを感じ、ストレスにつながりかねません。両者をなめらかにつなぐことで、顧客の満足度は高まり、エンゲージメント向上に貢献するのです。
例えばウェブサイトで店舗の在庫状況を確認できるようにしたり、オンラインで購入した商品を店舗で受け取れるようにしたりする仕組みが挙げられます。また、店舗のイベント情報をアプリで通知することも有効です。どちらの接点でも、同じように質の高い体験を提供することが重要です。
効果測定→PDCAの実践
最後のステップとして、実行した施策の効果を測定し、PDCAサイクルを回して継続的に改善していくことが不可欠です。顧客エンゲージメントの向上は、一度施策を行って終わりではありません。市場や顧客のニーズは常に変化するため、やりっぱなしでは効果が持続しないのです。施策の効果をデータで客観的に評価し(Check)、その結果を基に次の計画を立て(Plan)、実行する(Do)というサイクルを繰り返します。
具体的には、NPS®やLTVといった指標を定期的に観測し、施策全体がエンゲージメント向上に貢献しているかを確認することが重要です。地道な改善の継続が、着実な成果につながります。
顧客エンゲージメントの分析に役立つ指標(KPI)

顧客エンゲージメントの分析には、具体的な行動や状態を数値で測るためのKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。エンゲージメントという抽象的な概念を具体的な数値目標に落とし込むことで、チーム全体で目指す方向性が明確になります。また施策の進捗状況や成果を客観的に評価し、データに基づいた意思決定を行うためにもKPIは必要です。
どの施策が効果的で、どこに改善の余地があるのかを判断する基準となります。ウェブサイトでの平均滞在時間や再訪問率、SNSでの「いいね」やコメント数、メールマガジンの開封率などがKPIとして設定されるのが一般的です。これらの数値を定期的に追跡し、目標の達成度を評価していくことが大切です。
顧客エンゲージメント向上におすすめのツール

顧客エンゲージメント向上には、AI営業アシスタント「Notta Sales Agent」を活用するのがおすすめです。Notta Sales Agentを使えば、営業担当者が顧客との対話に集中できる環境が整えられ、良好な関係を構築できます。
具体的な機能としては、オンラインでの商談内容をAIが自動で文字起こし・要約し、重要な発言や決定事項をSalesforceなどのCRMへ自動で入力してくれます。営業担当者は議事録の作成業務ではなく、本当に必要な業務に集中することが可能です。さらに蓄積された対話データから顧客のニーズや課題を正確に把握できるため、一人ひとりに合わせたきめ細やかなフォローアップができます。
対話の質を向上させることで、顧客との深い信頼関係、つまりエンゲージメントの向上に直接つながるのです。
まとめ|自社に合った小さな改善から始めよう
顧客エンゲージメントとは、企業と顧客の間に生まれる深い信頼関係であり、現代のビジネスにおいてその重要性は増すばかりです。顧客との強い結びつきは、LTVの向上や価格競争からの脱却など、企業に多くのメリットをもたらします。
エンゲージメントを高めるには、顧客体験の設計からデータ活用、双方向の対話まで、多角的なアプローチが必要です。エンゲージメントの向上を効率化するためには、ツールの活用も欠かせません。Notta Sales Agentなら、シームレスなデータ管理で顧客との対話をスムーズにできます。
気になる方は、公式ホームページから試してみてください。

Nottaが選ばれる理由は?
① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応
② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化
③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く
④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成
(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)
⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン