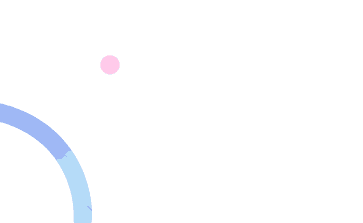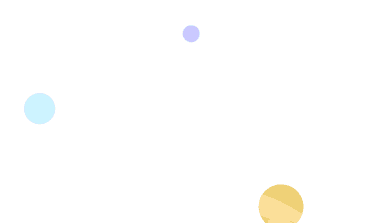【図解】SECIモデルとは?暗黙知と形式知のサイクルでイノベーションを生むナレッジマネジメント手法を事例と共に解説
業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

「あのベテラン社員がいないと、業務が回らない」 「個人の経験や勘に頼ってしまい、ノウハウが組織に蓄積されない」
多くの企業で、このような「属人化」が深刻な課題となっています。個人の能力に依存した組織は、その人が退職・異動した途端に競争力を失うリスクを常に抱えています。
この課題を解決し、個人の知識を組織全体の「資産」に変える経営理論がナレッジマネジメントです。そして、その中核をなすフレームワークが、今回ご紹介する「SECIモデル(セキモデル)」です。
SECIモデルは、個人の持つ経験や勘といった言葉にしにくい知識(暗黙知)を、誰もが理解し活用できるマニュアルやデータ(形式知)に変換し、組織全体で共有・発展させていくプロセスを示したものです。
この記事を読めば、以下のメリットが得られます。
SECIモデルの基本から応用まで、図解で体系的に理解できる
「暗黙知」と「形式知」を組織内で循環させ、イノベーションを生み出す具体的な方法がわかる
明日から自社で試せる実践のヒントや、他社の成功事例から学べる
SECIモデルは、世界的に評価されている経営理論であり、変化の激しい現代を勝ち抜くための強力な武器となります。ぜひ最後までお読みいただき、貴社の組織力強化にお役立てください。
SECIモデルとは、継続的なイノベーションを生み出す知識創造のフレームワーク
SECIモデルとは、個人の知識を組織的に共有・発展させ、組織全体の「知識創造」を継続的に促すためのフレームワークです。まずは、その基本的な概念と、理解に不可欠な2つの知識について解説します。
提唱者・野中郁次郎氏による「知識経営」の中核理論
SECIモデルは、一橋大学名誉教授である野中郁次郎氏と竹内弘高氏が、共著『知識創造企業』(1996年)の中で提唱した理論です。日本企業の強さを分析する中で見出されたこのモデルは、「知識経営(ナレッジマネジメント)」の概念を世界に広め、経営学に大きな影響を与えました。
その目的は、個人のひらめきや経験といった目に見えない知識を、組織全体で共有できる形式に変え、新たな製品開発やサービスの改善、業務革新といったイノベーションへと繋げることにあります。
SECIモデルを理解する上で不可欠な「暗黙知」と「形式知」
SECIモデルは、「暗黙知」と「形式知」という2種類の知識が相互に変換されることで機能します。この2つの違いを理解することが、モデルを学ぶ第一歩です。
暗黙知(Tacit Knowledge)
暗黙知とは、個人の経験や勘、感覚に基づいており、言語化するのが難しい主観的な知識を指します。長年の経験で培われた「コツ」や「ノウハウ」がこれにあたります。
例:
ベテラン職人が持つ、機械の微妙な音を聞き分ける技術
優れた営業担当者の、顧客との絶妙な間合いの取り方や交渉術
料理人が持つ、レシピには書かれていない火加減や味付けの感覚
形式知(Explicit Knowledge)
形式知とは、文章や図、数式、データなどを用いて言語化・視覚化され、誰もが共有できる客観的な知識を指します。
例:
業務マニュアル、手順書
設計図、仕様書
売上データ、市場分析レポート
企画書、プレゼンテーション資料
組織の成長とは、個人の持つ優れた「暗黙知」を、いかにして組織全体の「形式知」に変え、それを活用してさらに質の高い「暗黙知」を生み出していくかにかかっています。SECIモデルは、この循環を意図的に作り出すための具体的なプロセスを示しているのです。
SECIモデルの4つの知識創造プロセス
SECIモデルの名称は、知識を変換する4つのプロセス、Socialization(共同化)、Externalization(表出化)、Combination(連結化)、Internalization(内面化)の頭文字から取られています。
この4つのプロセスが循環し、螺旋(スパイラル)を描くように繰り返されることで、組織の知識は質・量ともに向上し、大きなイノベーションへと繋がっていきます。
それでは、各プロセスを具体的に見ていきましょう。

1. 共同化(Socialization):暗黙知から暗黙知へ
共同化は、同じ体験を共有することを通じて、個人の暗黙知が別の個人へ直接的に移転されるプロセスです。言葉を介さず、「見て学ぶ」「体で覚える」といった形で知識が伝承されます。
プロセス:個人(暗黙知) → 個人(暗黙知)
具体例:
OJT(On-the-Job Training)で、先輩の仕事ぶりを隣で見て学ぶ
顧客訪問に同行し、商談の進め方を肌で感じる
雑談や飲み会、合宿でのインフォーマルな対話から、相手の考え方や価値観を理解する
同じ課題について議論するブレインストーミング
成功のポイント:
形式張らない自由な対話の「場」を意図的に設けること
従業員が本音で話せる「心理的安全性」の高い環境を確保すること
2. 表出化(Externalization):暗黙知から形式知へ
表出化は、個人の持つ暗黙知を、言葉や図、コンセプトといった形式知へと変換・表現するプロセスです。これはSECIモデルの中で最も重要かつ困難な部分とされています。頭の中にあるモヤモヤとしたアイデアを、誰もが理解できる形に落とし込む作業です。
プロセス:個人(暗黙知) → 組織(形式知)
具体例:
熟練者のノウハウをヒアリングし、業務マニュアルを作成する
顧客への提案内容を企画書にまとめる
業務日報に、その日の業務で得た「気づき」や「学び」を言語化して記述する
製品開発のコンセプトを、キャッチコピーや設計思想として言語化する
成功のポイント:
対話やディスカッションを通じて、考えを明確にしていくこと
メタファー(比喩)やアナロジー(類推)を用いて、直感的なイメージを言葉にすること
完璧を目指さず、まずは不完全でも言語化してみるという文化を醸成すること
3. 連結化(Combination):形式知から形式知へ
連結化は、既存の形式知と、新たに生み出された形式知を組み合わせ、より体系的で新たな形式知を創造するプロセスです。バラバラに存在していた情報を整理・統合し、付加価値の高い知識体系を構築します。
プロセス:組織(形式知) → 組織(形式知)
具体例:
複数の市場調査レポートを統合し、全社的な経営戦略レポートを作成する
社内に散在する企画書や議事録をデータベース化し、誰もが検索・活用できるようにする
顧客からの問い合わせ内容と回答をFAQとしてまとめ、社内ナレッジベースを構築する
既存のマニュアルを統合・改訂し、より分かりやすい手順書を作成する
成功のポイント:
情報を一元管理し、効率的に整理・検索できるITツール(社内Wiki、ナレッジベースなど)を活用すること
情報の分類ルールを定め、誰もが必要な情報にアクセスしやすくすること
4. 内面化(Internalization):形式知から暗黙知へ
内面化は、体系化された形式知を、個人が実践を通じて自分のものとし、新たな暗黙知として体得するプロセスです。マニュアルを読むだけでなく、実際にやってみることで知識が血肉となり、応用力が身につきます。
プロセス:組織(形式知) → 個人(暗黙知)
具体例:
作成されたマニュアルを読み込み、トレーニングやロールプレイングを繰り返す
成功事例(形式知)を学習し、自分の業務に応用してみる
フライトシミュレーターでの訓練など、シミュレーションを通じて学習する
成功のポイント:
「習うより慣れよ」の精神で、実践の機会を数多く提供すること
実践に対するフィードバックを行い、学びを深めるサイクルを作ること
この「内面化」によって得られた新たな暗黙知が、次の「共同化」のプロセスへと繋がり、SECIモデルのサイクルは再び回り始めます。このスパイラルを何度も繰り返すことで、組織の知識はより高度なものへと進化していくのです。
SECIモデルを活用した企業のナレッジマネジメント成功事例
理論を学んだところで、実際に企業がどのようにSECIモデルを活用して成果を上げているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
ケース1:エーザイ株式会社|現場のナレッジを形式知化し、イノベーションを促進
日本の大手製薬会社であるエーザイは、早くからナレッジマネジメントに取り組み、SECIモデルを実践している企業として知られています。
背景・課題: 医薬品の営業担当者(MR)が、医師や患者との対話から得られる貴重な情報(副作用、患者の悩みなど)は、個人の暗黙知として属人化していました。
実践内容:
【表出化】 全MRに対し、日々の活動で得た気づきや患者の声を詳細なレポートとして提出することを義務化しました。これにより、現場の暗黙知が形式知へと変換されました。
【連結化】 蓄積された膨大なレポート(形式知)を専門部署が分析・統合し、新たな医薬品のニーズや効果的な情報提供の方法といった、より高次の形式知を創出しました。
【内面化・共同化】 分析結果を全社で共有し、MRが学習(内面化)。さらにその知識を基に、MR同士がディスカッションを行い(共同化)、新たな営業戦略や製品開発のアイデアを生み出しました。
結果: 現場起点のイノベーションが促進され、顧客満足度の向上や新たな価値創造に繋がりました。
ケース2:富士フイルムホールディングス株式会社|異分野の技術を連結し、新規事業を創出
写真フィルムのトップメーカーであった富士フイルムは、デジタル化の波により主力事業が縮小する危機に直面しました。しかし、SECIモデルの「連結化」を巧みに活用し、見事な事業転換を成し遂げました。
背景・課題: 写真フィルム市場の急激な縮小という経営危機に対し、既存技術の新たな活用法を見出す必要がありました。
実践内容:
【連結化】 同社が長年培ってきた技術資産(形式知)を棚卸ししました。その中で、写真フィルムの主成分である「コラーゲン」に関する高度な技術と、写真の色あせを防ぐ「抗酸化技術」という、一見異なる分野の形式知を組み合わせることに着目しました。
【表出化・内面化】 これらの技術が人間の肌の老化防止に応用できるのではないかという仮説(新たな暗黙知の表出化)を立て、研究開発を推進。化粧品事業という全く新しい領域に参入し、技術者たちは新たな知識を実践の中で体得(内面化)していきました。
結果: 高機能化粧品ブランド「アスタリフト」の開発に成功。ヘルスケア領域を新たな収益の柱として確立し、事業の多角化を実現しました。
各事例から学ぶ成功へのヒント
経営トップの強いコミットメント:知識の共有と創造を、単なる現場の取り組みではなく、全社的な経営戦略として位置づけることが重要です。
知識共有を評価する仕組み:優れた知識を共有した従業員を評価するなど、ナレッジマネジメントへの貢献が報われる人事制度や文化を醸成することが有効です。
対話の「場(ba)」のデザイン:SECIモデルの各プロセスを促進するような、物理的・仮想的な「場」を意図的にデザインすることが成功の鍵となります。
SECIモデルに関するよくある質問(Q&A)
Q1:SECIモデルを導入する上で最も重要なことは何ですか?
A1:経営層がナレッジマネジメントの重要性を深く理解し、継続的に推進する意思を社内に示すことです。また、それと同時に、従業員が失敗を恐れずに意見を言え、安心して知識を共有できる「心理的安全性」の高い組織風土を醸成することが不可欠です。
Q2:「表出化(暗黙知の言語化)」が特に難しいです。何かコツはありますか?
A2:対話が鍵となります。一人で抱え込まず、1対1のインタビューやグループディスカッションを通じて、聞き手が「なぜそう思うのか?」「具体的にはどういうことか?」と質問を投げかけることで、本人が無意識だった知識(暗黙知)の輪郭が明確になり、言語化しやすくなります。
Q3:SECIモデルはどのような企業に向いていますか?
A3:業種や企業の規模を問わず、あらゆる組織で活用可能です。特に、技術革新のスピードが速い業界、ベテランから若手への技能伝承が課題となっている製造業、顧客との深い関係構築が重要なサービス業などでは、大きな効果が期待できます。
Q4:SECIモデルを回すための具体的な「場(ba)」とは何ですか?
A4:SECIモデルにおける「場(ba)」とは、知識創造が生まれる物理的・仮想的な空間や文脈を指します。例えば、「共同化」のための雑談スペースやカフェテリア、「表出化」のためのブレインストーミング会議、「連結化」のための社内Wikiやデータベース、「内面化」のための研修室やOJTの現場などが挙げられます。
まとめ:SECIモデルで組織の知識を未来の資産に変えよう
最後に、本記事の重要ポイントをまとめます。
SECIモデルは、個人の暗黙知と組織の形式知を相互に変換・循環させることで、組織的な知識創造を促すフレームワークである。
「共同化 → 表出化 → 連結化 → 内面化」の4つのプロセスが螺旋状に繰り返されることで、組織の知識は質・量ともに成長する。
成功のためには、経営の強いコミットメント、心理的安全性、そして各プロセスを促進する対話の「場(ba)」のデザインが重要である。
SECIモデルは、単なる理論ではありません。それは、組織に学習とイノベーションの文化を根付かせ、予測不可能な時代を乗り越えるための、実践的な羅針盤です。個人の持つ輝かしい知識を、一部の人のもので終わらせず、組織全体の力に変えていきましょう。
参考文献
[1] 新規事業で異業種の化粧品に挑戦した富士フイルムの戦略~オープンイノベーションの重要性

Nottaが選ばれる理由は?
① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応
② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化
③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く
④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成
(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)
⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン